Good job プロジェクト
2024グリーンフェス 事務局として運営に携わりました。
皆様グリーンフェスにご参画頂きありがとうございました。
事務局の増田です。
事務局をやった感想としてはまず、本当に大きな成長をさせてもらえたなと思いました。

グリーンフェスを行うにあたって、盛り上げていくには誰一人かけてはならないのだなと感じました。
始めた当初は南桜井に一度も行ったことがなく、こんな場所があるのかといった感じでした。しかしポスターを貼りにお店に寄ったり、ポスティングをしに沢山街を歩き回った結果、今では地元越谷よりも知る場所になりました。


皆さん快くポスターを貼っていただき、今までは友人間でしか交流をしないようにしてきたのですが、皆さんと交流をすることで人と接することへの楽しさなども学べた気がします。

それから地元の庄和高校の生徒会の子達とも接し、年上の方と接することとは要領が違い、どう話していいのか迷っていました。しかし本番までには普通に話せるようになり、一致団結をして行えたことがすごく嬉しく思いました。

グリーンフェス本番の印象としてはあっという間だったなと感じました。ブース出店者の方々とお話をさせて頂いたり、写真を撮っていたらすぐに時間が過ぎて行ってしまいました。

私は高校の文化祭や体育祭といったイベントごとに本気で取り組んだことが無く、本気で大勢の人間と何かを成し遂げるという意味では、初めての経験をさせてもらえたなと思いました。


本番が終わった後の感じとしてはふわふわした新鮮な気持ちでいます。恐らく初めての感覚なので言語化できないのですが、そのうちこの気持ちというのが理解できる日が来るのではないかと思っています。来年もまたよろしくお願い致します。
本当に皆様グリーンフェスを一緒に作り上げていただきありがとうございました。
コミュニティ経営の視点から 中小企業の人的資本について考える<春のてらこや2024>

🌸JES 春のてらこや2024 概要 🌸
コミュニティ経営の視点から 中小企業の人的資本について考える
<日時> 2024年1月19日(金)17:00~18:50(16:45よりZoom受付開始)
<タイムスケジュール>
・オープニング・開会にあたり
・ご挨拶(影山摩子弥先生)
・トークセッション1:人事のフィールドから人的資本経営をどう捉えるか
(清水秀城さん・畑中義雄さん/モデレーター 金野美香)
・トークセッション2:コミュニティ経営の視点から人的資本について考える
(影山摩子弥先生・清水秀城さん・畑中義雄さん/モデレーター 金野美香)
・閉会あいさつ
<ゲスト>
◍ 影山 摩子弥 先生(横浜市立大学都市社会文化研究科 教授)
◍ 清水 秀城 さん(社会保険労務士/社労士事務所HR人事支援研究所 代表)
◍ 畑中 義雄 さん(社会保険労務士/有限会社人事・労務チーフ人事コンサルタント)
*モデレーター:金野美香(一般社団法人日本ES開発協会 理事長)
<参加費について>
◆参加チケット:2,000円(税込み)
◆ドネーションチケット:2,500円(税込み)
※参加者の皆さんには、後日アーカイブ動画をお送り致します。
※今回のセミナーの模様は、「TERAKOYA オンライン」にて録画動画を公開致します。
TERAKOYA オンライン▼
※ドネーションチケットとしてのご支援は、当協会Good Job アクション「子どもたちの”はたらく”体験・はたラボ」運営に充てさせていただきます。
🌳Good Job アクション!
https://hataraku.jinji-es.com/goodjob/action.html
🌸 お申込み
お申込みいただきましたメールアドレスに、お支払いとZOOMのURL等、詳細のご案内をいたします。
「さとのば大学」に学ぶ 日本の未来を変えていく新しい学習コミュニティ~「あるもの探し」で自分や環境の捉え方を変える~
(有)人事・労務や日本ES開発協会の活動にインターンとして関わらせていただいております、横浜市立大学国際教養学部1年の森愛里です。

「太陽のもとのてらこや」1日目に、株式会社アスノオト代表取締役の信岡良亮さんにオープニングセミナーを行っていただきました。そのお話のなかで感じたことや学んだことを共有させていただきたいと思います。
私は「学ぶ」ということに関してどこか退屈な、みんなで机に向かってするようなイメージを持っていました。ですが今回のお話は、私の考えを根底から覆すような内容で、驚きと発見の連続でした。
まず、「さとのば大学」について。2019年からスタートした4年制の大学で、日本全国の地域をめぐりながら学びを深めていきます。地域の人と関わりながら「暮らす」ということを体感し、少子高齢化などの社会問題を身近なものとしてとらえることが出来ます。実際に自分の体で地域に出向くので、学びの内容は人によってさまざまで、設定された25の地域をめぐる順番も人によって違うそうです。みんなで同じ内容をなぞるのではなく、人によって学ぶ内容が違うというのがとても興味深かったですし、私の実体験としても、教室で受けた授業よりも遠足や就学旅行、社会科見学など、自分の足で実践的に学んだ内容の方がずっと鮮明に記憶に残っています。生徒が退屈せずに楽しく学べるだけでなく、より多くの学びや発見が得られるシステムだと感じました。

また、お話の中で特に印象的だったのが「あるもの探し」についてです。人は「ないもの」について考えがちで、どうしてそれが自分に備わっていないのだろうかと、ネガティブに考えてしまいます。しかしそれは、自分にはあまり関係のないものであることが多いのです。例えばある田舎で「高いビルがない」「大きな商業施設がない」などの不満があったとします。それが全くその地域に関係のないものなのかどうかは見方にもよりますが、田んぼがずっと続くような田舎道に突然巨大なビルが建つというのは現実的ではありませんし、それよりもそこに備わっている自然や畑などのほうが、その地域の人と密接に関わるものです。田んぼや畑が多くある田舎なら、そこに住む人たちは地域で採れた米や野菜を食べて生活しているかもしれませんし、そこに広がる自然に魅力を感じて移住してきた人もいるかもしれません。自分に紐づいた「あるもの探し」がとても大切なことなのだと実感できました。

私も自分にないものについて考えて、人を羨んだり、どうして自分はこうなのだろうと落ち込んだりすることがありますが、私にはこんな特徴がある、こんなことが得意だと考えると、気分も明るくなってより前向きに物事に取り組めるようになりました。学生の間も、社会人になってからも心がけていきたい考え方です。

能動態・受動態の真ん中の中動態に関するお話もありました。能動態は自分が動く、他者と関わるというよりは自分が重視され、受動態は逆に他者に物事を与えられる、他者を重視した考え方です。この真ん中の「中動態」は、単純なする・されるの枠組みには入らない状態で、自分だけが動くわけでもなく、他者の下に自分がいるというわけでもなく、共に成長を見守り合うフェアな関係です。立場は違っても同じ方向を向いて歩きます。これは学びの場だけでなく、働いたり人と関わったり、どんな場面においても大切なことだと感じました。

全体を通して実践的なお話が多く、自分の私生活にも取り入れていきたいと思う考え方が多くありました。今回のセミナーで学んだ「あるもの探し」や「中動態」などを心がけて、これからの学校生活や人との関わりをより有意義なものにしていきたいと思います。
日光街道はコミュニティツーリズムの舞台
「太陽のもとのてらこや」三日目の行程は、栗橋→古河→野木→間々田、とご縁の深いまちを歩き進む一日です。
徒歩行軍チームはコツコツと歩き進み、古河を経て野木神社さんで、毎回取り組ませていただいている落ち葉掃きのあと、早めのランチタイム。

七五三のお参りの家族が集まる晴れやかな空気の境内で、できたておにぎりをいただきながら、午後の長い道のりに向けて力を蓄えました。

同じ頃、スケッチを終えたまちあるき一行は、坂長さんでの休憩を終えて、古河のまちのつながりの基点・鈴木園さんへ。

お伺いするたびに、古河のまちの歴史や文化という縦軸と、人々の暮らしかたや近隣のまちとの関わりといった横軸、の両面から、まさに多層的に重なりあう地域の姿をお伝えくださる石川代表。

お茶で一服しつつ、抹茶アイス・抹茶ソフトを皆でいただきながら、今回もお話をお伺いしました。

その後は、903シティファーム推進協議会の田心カフェで仕入れさせていただいている杉本納豆さんにも立ち寄り。

「このまま古河で一日を過ごしたいね」という声が聴こえてくるほどの、つながり豊かなまちあるきとなりました。
この三日目行程を歩いていると、「コミュニティ・ベースド・ツーリズム(コミュニティツーリズム)」という言葉の意味を体感します。
地域コミュニティが主体となり、その土地の歴史や文化、そこに住む人たちの暮らしの智慧そのものをコンテンツとして巡っていく形をコミュニティツーリズムと呼ぶのですが、わたしたちが「太陽のもとのてらこや」で行なっているのも、まさにコミュニティツーリズムの姿。
 (古河歴史博物館では、特別に”ストリートオルガン”を演奏してくださいました。オランダとも交流があった江戸時代のインフルエンサー(?)鷹見泉石さんにちなんでオランダ製。圧巻でした。)
(古河歴史博物館では、特別に”ストリートオルガン”を演奏してくださいました。オランダとも交流があった江戸時代のインフルエンサー(?)鷹見泉石さんにちなんでオランダ製。圧巻でした。)
歩きながら土地に埋め込まれたものを掘り起こし、地域の方たちとの関わりを通じて魅力あるコンテンツとして編集しながら、その地域で暮らす方たちの協力のもと、まちをめぐったり道を歩いたりしています。

栗橋・古河・野木と歩き進むと、日光街道の真ん中の宿場町・間々田に到着するのですが、この間々田も含めてコミュニティツーリズムが創られているのです。

間々田では、徒歩行軍もまちあるきも、「蛸屋間々田店」さんに立ち寄り。

毎年ご挨拶させていただく酒井さん・鈴木さんというスタッフお二人と、JES活動を共に推し進めている社労士・小池さんのご家族とが、とても温かなおもてなしをしてくださいました。

きっと、江戸の宿場町の時代からずっと、こうやってヨソからやってきた一行を「ようこそ」「お茶飲んで行きなさい」「この先も気を付けてね」と受け入れてくれる素地・気風が土地に刻まれてきたんだろうなあ、とこのエリアを通るたびに思うのです。
古河のまちを舞台にしたアートワーク
日光街道沿いの好きなまちランキング(JES調べ🌝)で必ずトップ3に入るまち・古河。
古河公方の本拠地、古河城の城下町、そして日光街道の宿場町…と、土地の記憶が積み重なり、情緒あるまちなみや地域に根付いた愛着心と誇りに触れられることがとても居心地よく、歩きがいのあるまちです。
今回、その古河で、 #みんなでつくるアート部 の皆さんがアートワークを進めてくださいました。

上野のまちでは、アート部の中根さん(書道家)にVTS(対話型鑑賞)を行なっていただきましたが、今回は、ガイド役を峯村さん(多摩美術大学)が担ってくださり、皆でスケッチに取り組みました。
まずは、古河歴史博物館で土地の歴史に触れたあと、スケッチとは何か?など峯村さんから説明。
そして、小さなスケッチブックを手に、お隣の「鷹見泉石記念館」へ向かいました。
 下見の際に、記念館の方にわたしたちの活動のことをお伝えしていたので、この日は、その担当の方がいろいろと声がけもしてくださり、温かい空気の中でスケッチがスタート。
下見の際に、記念館の方にわたしたちの活動のことをお伝えしていたので、この日は、その担当の方がいろいろと声がけもしてくださり、温かい空気の中でスケッチがスタート。
おもいおもいの場所で、じっくりと対象物と向き合う静かな時間が過ぎてゆきました。
峯村さん曰く、大切なのは以下の三つ。
①興味があるものに焦点をあてる(よく観察する)
②楽しく、すばやく描く
③構図を意識する
そして、描いて終わりではなく、
・何を描いたのか
・どうしてそれを描こうと思ったのか
・描く時に意識したいポイント
これらをスケッチブックの裏側に書き留めておき、スケッチを終えたあとに皆でふりかえりの場を持ちました。

「なるほど、だからあの場所にずっといたんだね」「これを描いていたのは、そういう意味だったんだ!」など、お互いの一枚を通して、豊かな対話が生まれる場に。
スケッチを終えたあとは、古河のまちに古くからある蔵を改築したコミュニティスペース「坂長」でランチ。
親戚の集まりのようなアットホームな雰囲気の中、皆で「いただきます」。
天保年間創業の古河のお米屋さん・安井米店のおにぎり弁当をほおばりながら、お互いのスケッチブックを見せ合ったりとにぎやかに時間が過ぎて行ったのでした。

観たり聴いたり、という五感を受け身に作動させるだけでなく、「描く」という主体的なアクションを起こすことによって、こころとからだが開き、その土地のさまざまな情報に触れやすくなり、気づきが深まる。
今回のアートワークは、そのような体験の機会でした。
「その土地との関わりを深め、その場を利用して自己実現していくひとが『関係人口』である」と[は、かつてこの古河のまちでブラタモリ的な散策の時間を作ってくださった石井造園・石井社長の言葉ですが、スケッチを通してその土地に埋め込まれた多様な情報に触れながら、描く・伝えるといった主体的な行動を促してくれるアート部のこころみも、地域の関係人口を増やす重要な役割を果たしているのではないかと思います。

「さとのば大学」に学ぶ 日本の未来を変えていく新しい学習コミュニティ
2023年11月3日、“日光街道太陽のもとのてらこや”オープニングセミナーで行われた「さとのば大学」発起人・信岡良亮さんによるセミナーに参加しました。
地域を旅する大学・さとのば大学では、地域をめぐり暮らしながら学ぶ「越境学習」として、自分で選んだ地域を1年毎に地域留学する取り組みをされています。

関西出身の信岡さんは、東京でITベンチャーでの経験を経て、会社を軸にするのではなく自分の力で働くことの大切さを学んだそうです。その後2年半ほどWebのディレクターとして働き、大きすぎる経済の成長の先に幸せな未来があるイメージが湧かなくなったことを機に25歳で島根県の海士町に移住。
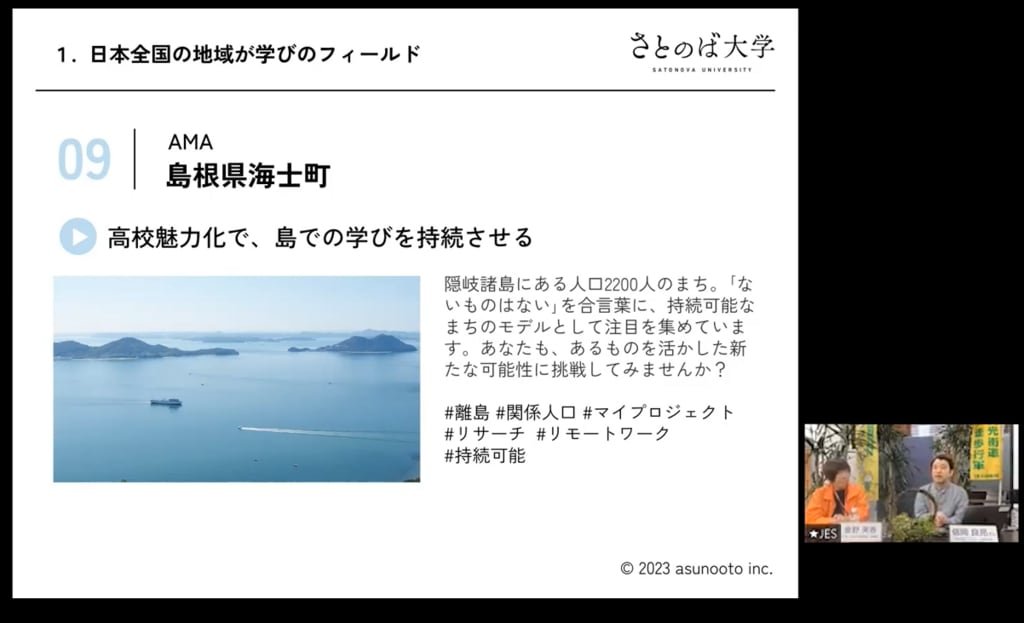
都会での生活はお金を稼げば生活がまわり、社会と接続しなくて良い。一方で海士町では贈与経済でなければ暮らしが回らなかったといいます。移住して何を行うかと言うと、島のコンテンツを発見する冒険から始まるとのこと。何かが当たり前にある暮らしではなく、ないから探すところから始まるのだそうです。
信岡さんは海士町に移住し、「自治」を身近に感じる機会が増えたといいます。「等身大の社会課題をまちという単位で改善してくプロセスが楽しい」その言葉が印象的でした。都心に近いとまちの単位が大きく、「自治」がどこか遠くのことのように感じられますよね。「未来のコミュニティを一緒に作っているのが楽しい」という信岡さんの言葉にあるように、自分が関わることで未来が変わっていくという期待値が人を動かす原動力になっているように感じました。

地域を越えて交流する「越境学習」により、日常では何も変わらなかった景色に彩りが加わります。さとのば大学で地域留学をするとまず自分が行った地域で、「あなたは何をしにきたの」という問いから始まります。「私、何者だっけ」と365日問われます。1年その地域に住み、慣れてきた頃にまた新たな地域での留学が始まることで、1年目に考えていた「何がしたい」がより芯のあるものになっていき、意志を持って行動することができるように。
自分にとって慣れ親しんだ環境、コンフォートゾーンを飛び出していくことで良質な問いが生まれます。会社で働いていると、「〇〇銀行の〇〇」と名乗ることになり、肩書があることで「あなたは誰か」という問いに向き合う必要がなくなります。肩書がある安心感とともに、肩書があることでコンフォートゾーンを知らぬ間に作っているように思います。

さとのば大学では4つの地域を交流することで、4つの地域のアイデンティティをもらえます。アイデンティティは自分だけに拠るものではなく、お裾分けすることもでき、アイデンティティは地域を旅した関係性の中で育まれていきます。「イントラパーソナルダイバーシティ」信岡さんから出た、その言葉は、「自分の中の多様な一面を知り、自分自身を膨らませていくこと」。良いビジネスモデルもいいけれど、学び続ける文化を作ることの大切さについて語っていました。
学びは、成長や変化できる余白のことを指し、学びが楽しいのは自分の未来に希望を持てることを指すそうです。自分のアクションの先に、自分の描いた未来に繋がっていくと思えたら、学びが格段に楽しくなりそうですね。

「誰かが良くしてくれたらいいな」で終わらず、やる人を育てるためにも、全ての資源に誰かが手をかけていく仕組みづくりが大切とのこと。さとのば大学では、定性的なものを評価していくのは難しいけれど「さとのばWay」があり、それも含めて独自の指標で自己評価して対話しながら成長実感を持たせていくことで、学習コミュニティとして循環するエコシステムが構築されているようでした。

未来の”はたらく”を考える<あおぞら図書館えいが会>

日光街道のまち・みち・ひととの関わりから学びを深める「太陽のもとのてらこや」。
その舞台である宿場町で出合ったすてきなスペースをお借りして、あおぞら図書館えいが会を開催します。
今回の会場は、日光街道が行き着く場所である「日光東照宮」です。
えいが会のテーマは「未来のはたらくを考える」。
自分の、自分たちの、未来に向けた「はたらくかたち」「はたらきかた」「はたらく場」「はたらく力」をちょっと立ち止まって考え、まわりの人たちと話してみるー、そのような題材として映画を鑑賞し、キャリアについて考える場です。
そのため、映画を観たあとに対話・ワークの時間を設けていますので、「いろいろな世代のひとと交流したい」「他分野ではたらくひとの話を聴いてみたい」「なにか活動に参画してみたい」といったアンテナを持った皆さんの参加をおすすめします。
題材は、アフガニスタンとパキスタンで、現地の人々と共に現地の人々のために働いた医師・中村哲さんの生涯をドキュメンタリーでたどった映画「医師 中村哲の仕事・働くということ」をお送りします。
<セミナー概要>
●日時:令和5年12月2日(土)15:15 ~ 17:00
●プログラム
・15:15 開場:特別祈祷を終えてからお入りいただきます
・15:20 開会・ごあいさつ・チェックイン
・15:30 開演(映画は47分間です)
・16:20 休憩
・16:30 ワークショップ
・17:00 まとめ・閉会
●受講料:
一般5,500円/学生3,000円 ※特別祈祷代及びセミナー受講代含む
*本セミナーは、ドネーションチケットの形をとらせていただいております。皆さまの参加費の一部は、日光街道沿いの地域の子どもたちのはたらくワクワクを育むお仕事体験「はたラボ」の運営費および学生の活動参加費に充てさせていただきます。投げ銭として、上記受講料に加えてのご寄付もよろしければご検討ください。
<Good Job アクション!>
https://hataraku.jinji-es.com/goodjob/action.html
<えいが予告編>
https://youtu.be/bOSDk1o98ik
◎本セミナーは、「日光街道 太陽のもとのてらこや」のプログラムの一環として開催するものです。
https://hataraku.jinji-es.com/nikkou.html
「未来の新しい”はたらく力”を増やす」というテーマのもと日光街道を舞台に開催する「日光街道 太陽のもとのてらこや」では、フィールドワークをまじえながら五日間に分けて日光街道147キロを歩き進みます(各日参加可)。プログラムを通して目指すのは、”境を越えてつながりから価値を生み出す”働くかたちを学ぶこと。日光街道沿いの各地域で暮らす、「越境するはたらき方の実践者」「つながりの基点として地域を動かすコミュニティリーダー」「次世代の子どもたちへバトンをつなぐ立役者」「未来思考のはたらき方を自ら実践するロールモデル」に触れながら、自分たちの未来像を描くヒントを見つけ出す経験学習の場です。
日光街道は、未来を見据え国の礎を築いた徳川家康公を始め、農家出身で農業に従事しつつも武士としてさまざまな地域興しを担った二宮尊徳氏、外国人というよそ者の視点から当時の日本の姿を客観的に世界に広めたイザベル・バード氏など、多くの偉人が足跡を残した道です。
俳人松尾芭蕉の紀行作品「奥の細道」にも多く取り上げられ、日本人から愛されてきたこの地域にある、日本の旧くから続く「はたらく」に、これからのはたらくカタチのヒントがあるのではないかと思います。
<お申込み>
「さとのば大学」に学ぶ 日本の未来を変えていく新しい学習コミュニティ

学校だけに教育を担ってもらうでなく、官民も連携しながら地域全体で教育の機会を創り上げていこう、ということで、いま「地域教育」の重要性が問われています。
わたしたちの活動フィールドである日光街道沿いのまちに焦点をあてると、例えば街道の起点・日本橋では、地元企業や学生たちも参画し、地域について学ぶプログラムが実施されたり、宇都宮や春日部などでは、地域の中に学びを担う人材を育成したり、という動きが積極的に取り入れられつつあります。
また、いつもわたしたちの活動を支援くださっている石井造園さんは、横浜市をフィールドに、子どもたちと地域の緑を守る活動(ナラレンジャー)や、町内会などの自治組織と連携したCSR活動を通して、つながりの基点として地域教育を実践しています。
このような地域教育=地域を舞台にした新しい学びのかたちを日本で切り拓いてきたのが、今回ゲストでお呼びする信岡良亮さんです。
これから社会に出る若者たちが主人公となり、日本各地をフィールドに、地元の方たちとも連携を深め社会課題の解決にも寄与しながら、学びと実践を深めていく「さとのば大学」。今回、その発起人である信岡さんから、学校という枠を越えた未来思考の学びのあり方について、社会人のリカレント教育なども取り上げながら、お話を伺いたいと思います。
かつてこの「太陽のもとのてらこや」でお話をいただいた佐藤淳一さん(宮城県・雄勝中元校長)は、震災以降の地元中学生たちの姿をふりかえりながら「何もかもなくしてしまった彼らにこそ、自らがたくましく生きていく力を身につけ、将来どんな仕事に就くかを考える場・学ぶ場が必要である」と述べていました。かねてよりキャリア教育に力を入れてきた宮城県で、雄勝の町を舞台に職場体験の機会を広げてきた佐藤さんが、震災で地域が全てなくなってしまってからも、発想を変えて、さまざまな人とのつながりや資源を活かし修学旅行先の地域を舞台にした志教育を実践してきた、というものです。
いま、震災時に多感な小中学校時代を過ごしていた若者たちは、続々と社会に歩み出しています。
そのような次世代の子どもたち・若者たちが、創造性豊かな働きかたで自身のとくいを伸ばしていけるようなキャリアの道筋をたどるためには、いかに創造性豊かな学びを提供できるか、という点が重要だと考えます。それを、わたしたち民間企業も連携しながら、多様性あふれる地域を舞台にした学習機会を提供していくことが、一つの道筋と言えるのではないかと思います。
土地の歴史や文化という縦軸と、自然やひとなどの地域資源が広がる横軸が、多層的に重なりあう「地域」。それらの価値を編集し直し、繋げあわせることで、豊かな学びの舞台ができあがります。
日光街道や、参加する皆さんの目の前に広がる地域あるいは職場で、どのような実践をできるのか、信岡さんのお話を踏まえ、考えていく機会にできればと思います。
<セミナー概要>
●日時:令和5年11月3日(祝・金)10:30 ~ 12:15
*ハイブリッド開催(Zoom参加/リアル参加)
●プログラム
・開会あいさつ
・信岡良亮さん 基調講演 (聴き手:金野美香)
・トークセッション
・質疑応答
・謝辞・閉会あいさつ
●受講料:
Zoom参加の方 = 一般2,000円/学生1,000円
リアル参加の方=一般3,000円/学生1,500円
*リアル参加お申し込みの方は、「日光街道 太陽のもとのてらこや」初日(11月3日(祝))にご参加いただけます。
*本セミナーは、ドネーションチケットの形をとらせていただいております。皆さまの参加費の一部は、日光街道沿いの地域の子どもたちのはたらくワクワクを育むお仕事体験「はたラボ」の運営費および学生の活動参加費に充てさせていただきます。投げ銭として、上記受講料に加えてのご寄付もよろしければご検討ください。
<Good Job アクション!>
https://hataraku.jinji-es.com/goodjob/action.html
<ゲスト プロフィール>
信岡良亮(のぶおかりょうすけ)さん

関西で生まれ育ち同志社大学卒業後、東京でITベンチャー企業に就職。Webのディレクターとして働きながら大きすぎる経済の成長の先に幸せな未来があるイメージが湧かなくなり、2007年6月に退社。小さな経済でこそ持続可能な未来が見えるのではないかと、島根県隠岐諸島の中ノ島・海士町という人口2400人弱の島に移住し、2008年に株式会社巡の環を仲間と共に企業(現在は非常勤取締役)。6年半の島生活を経て、都市と農村の新しい関係を創るために東京に活動拠点を移し、2015年5月に株式会社アスノオトを創業。
現在は都市と地域を繋ぐ学びの場「地域共創カレッジ」を主催するほか、ビジネス・ブレークスルー大学の講師として「ITと地域イノベーション」の授業などを担当している。2018年より地域を旅する大学「さとのば大学プロジェクト」の発起人となり、2019年7月より開講し新しい学びの文化を日本に根付かせる活動を展開中。
◎本セミナーは、「日光街道 太陽のもとのてらこや」のプログラムの一環として開催するものです。
https://hataraku.jinji-es.com/nikkou.html
「未来の新しい”はたらく力”を増やす」というテーマのもと日光街道を舞台に開催する「日光街道 太陽のもとのてらこや」では、フィールドワークをまじえながら五日間に分けて日光街道147キロを歩き進みます(各日参加可)。プログラムを通して目指すのは、”境を越えてつながりから価値を生み出す”働くかたちを学ぶこと。日光街道沿いの各地域で暮らす、「越境するはたらき方の実践者」「つながりの基点として地域を動かすコミュニティリーダー」「次世代の子どもたちへバトンをつなぐ立役者」「未来思考のはたらき方を自ら実践するロールモデル」に触れながら、自分たちの未来像を描くヒントを見つけ出す経験学習の場です。
日光街道は、未来を見据え国の礎を築いた徳川家康公を始め、農家出身で農業に従事しつつも武士としてさまざまな地域興しを担った二宮尊徳氏、外国人というよそ者の視点から当時の日本の姿を客観的に世界に広めたイザベル・バード氏など、多くの偉人が足跡を残した道です。
俳人松尾芭蕉の紀行作品「奥の細道」にも多く取り上げられ、日本人から愛されてきたこの地域にある、日本の旧くから続く「はたらく」に、これからのはたらくカタチのヒントがあるのではないかと思います。
<お申込み>
お申込み受付は終了いたしました。
昔も今も日光街道の中間地点として愛されるまち、間々田
先日、日光街道の中間地点がある間々田周辺を散策してきました。まず、間々田駅から小山市立博物館に向かい、間々田の歴史に触れ、小山乙女河岸歴史公園へ立ち寄った後、乙女屋さんというお菓子屋さんでジェラートを頂いたり、浅野屋茂兵衛さんというお蕎麦屋さんでへぎそばを頂いたり、間々田紐を見たりしてから間々田八幡宮へ行きました。そして、蛸屋さんや思季彩館さんといったお店に立ち寄りながら小山駅まで歩いて行きました。

最初に訪れた小山市立博物館では、縄文時代から現代に至るまでの間々田の歴史を学ぶことができました。間々田に古墳ができ始めたのは他の地域と比較すると遅かったけれども、多くの古墳があったことを知り、遅れながらも発展していった地域なのだと思いました。特に小山評定以降から乙女河岸が注目されるようになり、物流の重要な拠点となっていたそうです。日光東照宮の造営と修復のための資材の陸揚げや江戸への年貢米の輸送などにおいて乙女河岸が大きな役割を担っていたことが分かり、関宿と境町の人々にとっては利根川がそうであったように、間々田の人々にとっては思川が江戸と繋がる大切な交通手段だったのだと感じました。川がどれほど大きな役割を果たしていたのか改めて感じることができました。

そして、大きく広がったきれいな田園風景を見ながら小山乙女河岸歴史公園に行くと、休憩所で休んでいた方が私の持っていた日光街道と書かれた旗を見て声を掛けてくださいました。何もないと口では言いつつ、日光街道の旗に気付いてくださったり、日光街道の中間地点があることを話してくださったりと間々田という地域に愛着を持っているように感じました。

小山市立博物館で学芸員をされていた方も旗を見て声を掛けてくださり、間々田には地域に愛着を持った温かい方が多いのだと思いました。
昼食後に訪れた間々田紐のお店には伝統的な組紐が並んでおり、組紐の体験をされている方もいらっしゃいました。素朴で可愛らしいものばかりでしたが、「帯〆は一度締めると緩まず、着崩れを起こさないのが特徴」という説明を見て、実用性の面でも活躍できる技術が詰め込まれていて素敵だと思いました。私も今度体験してみたくなりました。

その後に訪れた間々田八幡宮では、緑に生い茂った木々の中に多くの風鈴が飾られている光景に日本の夏を感じ、印象的でした。緑に囲まれた日陰の中できれいな風鈴の音色も聞こえ、涼しさを感じました。また、池には多くの鯉が泳いでおり、餌をもらいに集まる鯉の中にすいすい泳ぎながら入っていく小さな亀もいました。拝殿の下の隙間には猫がおり、涼んでいるように見えました。

自然に囲まれる心地よさと共に、生き物たちののんびりとした雰囲気も感じ、癒やされる空間でした。境内には「頼朝手植えの松」と呼ばれる松や「無事かえるの像」という可愛らしいかえるの像もありました。

939年頃に起きた平将門の乱の際に藤原秀郷という武将が間々田八幡宮や沿道の神社仏閣に戦勝を祈願し、乱を平定したと言われており、それを聞いた源頼朝も奥州藤原氏との合戦の際に間々田八幡宮を参拝し、戦勝を祈願して松を植えたとされています。そして、その松は「頼朝手植えの松」と呼ばれ、明治38年に枯死してしまうまで大切に守られ続けたそうです。現在、頼朝手植えの松は3代目となっており、代替わりしながら頼朝が間々田八幡宮を訪れた歴史を伝えてくれています。

間々田八幡宮には「古池や 蛙飛こむ 水の音 芭蕉翁」と刻まれた句碑もあり、その句碑の裏に「地元の名士であった田口久七が北越遊歴中に病に倒れた際に、故郷の間々田八幡宮を心に浮かべて一心に祈ったところ、病が癒え、無事に故郷に帰ることができ、その神恩に感謝してこの出来事を後世に伝えるためにその句碑を奉納した」というお話が書かれているそうです。そして、田口久七が故郷の鎮守の池に棲むかえるの姿に芭蕉の名句を重ねて伝えようとした、その感謝の思いに「無事かえるの像」というかたちが与えられて祀られているとのことでした。無事かえるの像が建立されたのは令和2年であり新しくできた像でしたが、これから頼朝手植えの松のように何百年も大切にされ、様々な歴史が刻まれていってほしいと思います。
その後、小山駅へと向かう道の途中で立ち寄った蛸屋さんには、どれを買おうか迷ってしまうほど美味しそうな和菓子がたくさん並んでいました。私はみかもの月と栗石がえしを頂きました。みかもの月はふわふわのスポンジの中にやさしい甘さのカスタードが入っており、栗石がえしはふわふわのスポンジの間にあんこと一粒の栗がそのまま挟まれており、どちらもとても美味しかったです。そして、思季彩館さんには808ブルワリーさんという小山市にあるブルワリーで製造されたクラフトビールなど、様々な小山市のものが並んでいました。

そこで私はオヤマエールという小山で採れたお米を使って作られたビールを頂きました。フルーティーな風味があり、普段あまりビールを飲まない私でも飲みやすかったです。

間々田の散策を通して、源頼朝や徳川家康といった誰もが知っているような歴史上の人物も訪れ、非常に大切にされていた地域であることを学びました。また、日光街道の旗を見て声を掛けてくださった方々とお話をして、そのような歴史に誇りを持つ地元の方々に愛されている地域であることも実感しました。間々田には今回訪れた場所の他にも逢いの榎や小山市車屋美術館など気になる場所がたくさんあるので、また訪れ、より多くの魅力に触れていきたいと思います。

「人」のつながりを感じた街歩き
私は、今日の関宿城博物館や境町を巡って、歴史には「人」の存在が不可欠であるという事を実感しました。まず、関宿城博物館では、川を移動した大事業についての歴史を学びました。

私達が日常目にしている川というものにも、川を中心として、集落や関所などが作られ、川を移動する事業という大プロジェクトに対しても、その地域の人の助けや努力によって作られていく。歴史というのは、「人」というものなしでは、語れないという事を実感しました。

そして、その「人」にとって重要なものである川という存在。その川は、今は釣りをしていたり、川遊びをしたりという実態があるのかもしれません。しかし、その川というものには、特に今回学んだ利根川には、氾濫を起こし続け、その周りの人を苦しめていたという歴史があります。その歴史の中で、江戸時代という、現代のように便利な自動的に機械がない時代に、小さな舟を使いながら、一つ一つ手を使って川自体の位置を変えていくのです。

それを変えるという作業をするのは、もちろん人の手が必要です。そしてそこには、「この利根川が氾濫をしないように、どうにかしよう!何かできることはないか!」という熱い思いがあり、一人一人が川の移動に携わっていたのではないかと考えます。

そして、その利根川の移動する過程の歴史を教えてくれた学芸員の方のお話の一つ一つが、私達を利根川の歴史の世界へ導いてくれました。その方からも、昔の利根川の工事をした方のように、利根川や関宿という町に関する歴史への熱意を感じる事ができました。川の場所を移動しなければならない理由や関宿周辺に住んでいた人々の歴史。なんら変哲のない道にも、そこには歴史の跡が隠されている。それが気になる方は、ぜひ関宿博物館に訪れてみてください!日常生活を見る視点がきっと変わります。

次に訪れた場所は、境町です。境町は、千葉県と茨城県の県境の近くにある町です。この町は、過去、今、未来をつなぐ町であると感じました。それが、地域の方々のお話を聞くことで、明らかになっていくのです。その舞台となったのが、自動運転バスです。境町は、日本で唯一完全自動運転のバスが走っている地域なのです。危険を察知し自動で停止したり、周りを見ながら、人間のように運転することができます。運転免許を取って1週間で車をすってしまった私よりも、確実に運転が上手なことを実感しました。

近未来の乗り物に乗りながら、地元の案内人の方にお話しをお聞きしました。その話の中で、境町は、最寄りの駅からバスで、30分程度かかるのにもかかわらず、あえて鉄道を通さなかったという事を聞いて驚きました。鉄道を通さなかったという背景には、その地域が誇りにしていること。つまり、水運の発達という理由があったのです。境町には、大きな川があり、昔、水運業が発達していました。その水運業を中心として、街が形成されていきました。そこには、時代が積み重ねてきた人々の想いや誇りがあるのではないかと考えられます。その理由として、鉄道という新しい技術を拒んだのではないかと予想ができます。鉄道の敷設を拒否したという事実を知るだけではなく、なぜ拒否するに至ったのかという背景を知る大切さも知ることができました。そして、自動運転バスという近未来なものと歴史が、交差しているように感じました。

最後に、境町にある今も昔も変わらなかった風景について紹介させていただきます。それが、「人」の存在です。水運業には、舟を導くための人がいます。そして、自動運転バスにもバスが正常に運行できるようにサポートをする人がいます。この2人には、共通点があるのです。それが、「案内人」としての役割です。そして、昔でもあっても、今であっても境町には、「案内人」を中心とした人々のつながりが溢れています。ずっと昔の水運業であっても、境町の今の地域の話をしたり、今の現状を話したりなどの対話が繰り広げられていたのではないでしょうか。その一方で、自動運転バスであっても、そのバスに乗車することで、その人を中心とした人のつながりが作られます。高齢者や子ども、観光客などがそのバスに乗車をし、「案内人」の方を中心とした人同士のつながりが作られるのではないでしょうか。今回の境町の街歩きを通じて、昔から現代へ続く人のつながりを感じることができました。









